皆さんは神社に行った時、インターネットなどで神社に関連する事を調べた時に、よく見かける用語や語句があるのではないでしょうか?私も最初は、分からない用語を調べた事がありますが、「その説明文の中に、更に分からない用語が出てきて、結局分からない」なんてもことよくありました。
今回はそんな困った事が解決できるように神社に関連する用語や語句を分かりやすく解説していきます。
御朱印巡りについて詳しく知りたい方は、御朱印巡りの魅力と意味の記事をご覧ください
参拝方法の基本である手水舎の使い方や注意点は、手水舎の作法・注意点まとめをご覧ください
要点を伝授/神道・神社の用語解説まとめ
今回は神社に関連した用語や語句を出来る限り分かりやすく、要点だけを絞って五十音順に、
まとめました。ボタンを押して頂いたらその行まで飛ぶことが出来るのでサクッと調べることが出来ます。
※随時、更新していくので用語・語句の追加修正はあります。
あ行/神道・神社の用語解説
| 用語 | 意味・解説 |
|---|---|
| 相殿(あいどの) | 主祭神に対して2柱以上の神を合祀または配祀した社殿。またその神。 |
| 葦原中国(あしはらのなかつくに) | 日本の国のこと。国土や地上のこと。 |
| 吾妻(あづま) | 関東地方のこと。 ヤマトタケルの妻が海の神の怒りを鎮めるために身を投げ、その際にヤマトタケルが「吾妻はや」と叫んだことが由来とされている。 |
| アニミズム(あみにずむ) | 自然崇拝とも呼ばれる。 すべてのものに霊魂が宿っているとする思想や信仰のこと。 自然物や無生物にも霊的存在を認めるこの考え方は、日本の神道とも深く関連している。 |
| 天つ神(あまつかみ) | 高天原出身の神様。国津神に対して称される。高天原におられる神また高天の原よりこの国に降臨せられた神。 |
| 天沼矛(あめのぬぼこ) | イザナギとイザナミが別天つ神からもらった、玉で綺麗に装飾された矛。 |
| 天磐船(あまのいわふね) | ニギハヤヒが 高天原から乗ってきた船。 |
| 天岩屋戸(あまのいわやと) | 天照大神アマテラスが引きこもった岩屋戸。 |
| 天御柱(あまのみはしら) | イザナギとイザナミが 淤能碁呂島(おのごろしま)で建てた神聖な柱。 |
| 天の浮き橋(あめのうきはし) | 高天原と葦原の中つ国の間にかかっている橋。 |
| 荒垣(あらがき) | 神社の外側を囲う目の粗い垣根のこと。 二、三重に設ける時は内を瑞垣、外を玉垣又は荒垣という。 |
| 荒魂(あらたま) | 神道における神様の霊魂のひとつ。 神の霊魂の、大きく分けて2つの異なった側面のことを指す。 荒魂とは、荒々しい側面を指しており、たとえば天変地異、病を流行らせ、人の心を荒廃させる、など活動的な一面を表す。 一般的に神の祟りというのは荒魂の現れであるとされる。荒々しく勇猛な側面を示し、神の力強さや威厳を象徴している。 荒御魂を祀る神社では、特に勝運・開運・厄除けなどのご利益があるとされている。 たけだけしく霊験あらたかな神。 |
| 案(あん) | 「やつはし」「八足(はっそく)」などと呼ばれることもある幅の狭いテーブルのこと。 合計8本の足がついているように見えることが名前の由来だと考えられるが、正式名称は「案」。 神饌や玉串などを置くために用いられることが多い。 神前結婚式などでは参列者の前に縁起物や土器(かわらけ)を乗せるために置かれていることもある。大小高低様々な種類がある。 |
| 一宮(いちのみや) | 平安時代から中世にかけて行われた社格の一種。諸国において由緒の深い神社、または信仰の篤い神社が勢力をもつことで神社の階級的順序が生じ、その首位にあるものが一宮。次に二宮。その次が三宮、四宮と順位を付けていった。 |
| 稲城(いなぎ) | 防御のために城の前に作る稲を積んだ柵。 |
| 忌火(いみび) | 神道において「清浄な火」を意味する。 宮中、伊勢神宮などの重要な祭において新しく起こされる火のこと。 神饌の調理やそのほかの神事に用いられる。他の神社においても鑽火神事(きりびのしんじ)として行われる。 |
| 慰霊祭(いれいさい) | 死者の霊を慰め、生前の業績を表彰し、功績を振り返り慕うことを目的とした祭祀。 |
| 磐座(いわくら) | アニミズムにおける信仰形態において、神が宿る・神が降臨するとされる岩のこと。 岩の大きさはさまざまですが、巨石が多く用いられます。 社殿を持たない時代には、祭祀や信仰の中心の場所となっていました。 |
| 誓約(うけい) | 上に誓いを立て、その結果によって吉凶や成否を占う行為。 日本神話におけるアマテラスとスサノオの間で行われた誓約が有名。 |
| 氏 子(うじこ) | 共通の氏神をまつる人々。 氏神が守護する地域に住む人々。 |
| 歌垣(うたがき) | 古代日本の、求婚や出会いを目的とした男女が集まって歌を詠み交わし交流を深める風習。 山や野原で開催される事が多かった。 |
| 内削ぎ(うちそぎ) | 千木の先端が水平に切られた形状。 伊勢神宮の内宮の千木が内削ぎ。 |
| 采女(うねめ) | 宮廷で天皇や皇后に仕え、食事や身の回りの雑事などの世話を専門に担当した女官。 |
| 産土神(うぶすなかみ) | 同一の地域内に居住する人々が共同でまつる神。氏神(うじがみ)とも言う。 自分の生まれた土地を守護する神のことで、その地に生まれた人を産子(ウブコ)という。 産土とは、生まれた土地・本拠の意味。 氏族を通じて結びつく神社と人との関係が氏神と氏子であり、土地を媒介として結びつくのが産土神である。 生まれる前から死んだ後までその人を守護するとされ、他所に移住しても一生を通じて守護してくれると信じられている。 産土神は初宮参りや七五三などの際に参拝されることが多く、その土地の神社に祀られている。 自分の生まれた土地を守護する神のことで、その地に生まれた人を産子(ウブコ)という。 今日では氏神も産土神も鎮守神も同じような意味で扱われている。 |
| 英霊(えいれい) | すぐれた人の霊魂。 特に戦死者の霊がそう呼ばれる。 |
| 絵馬(えま) | 祈願や感謝の意を込めて神社や寺院に奉納する、絵が描かれた木製の板。 古代には生きた馬を神に捧げていたが、次第に絵に描かれた馬が代用されるようになった。 多くの神社では、馬以外にもその神社にゆかりのある動物や縁起物が描かれている。 |
| 蝦夷(えみし) | 「えぞ」とも呼ばれる。北海道の古称。 また、そのに住んでいた人々をさすこともある。 |
| 延喜式(えんぎしき) | 平安時代に作られた日本の古代法律の詳細をまとめたもの。 年中行事や制度などの事務規定もまとめてある古代法典。法令集である三大格式(「弘仁格式」「貞観格式」「延喜式」)の一つ。 ほぼ完全な形で残っており現代では古代史の研究資料として重要なものとなっている。 |
| 円座(えんざ) | 藁と藺草(いぐさ)で編んだ厚手の円形の座布団。神職や参拝者が座るためのもの。 |
| 大麻(おおぬさ) | 大ぶりの榊の枝に紙垂や布と麻をくくりつけたお祓いの道具。 棒に多くのの紙垂と麻ひもをつけたものもよく見られる。 通常、これを左、右、左と三回振ってお祓いをする。 |
| 大祓(おおはらい) | 「おおはらえ」ともいう。 古来から宮中で行われた万民の罪穢を祓い除く儀式。 今日も宮中を始め全国各地の神社で行われており、人形に罪穢を託したり、茅輪をくぐって罪穢を祓う行事も行われる。 |
| 奥宮(おくみや) | 神社の一部で、通常は本宮よりも奥に位置する社殿のこと。 「奥社(おくしゃ/おくのやしろ)」「奥の院(おくのいん)」とも呼ばれ、山頂や山中に位置することが多い。 奥宮は本宮よりも参拝者が訪れるのが難しい場所にあることがほとんどで、より神聖な場所とされている。 |
| 折敷(おしき) | 三方の上の木のお皿の部分と考えるとよい。 三方と同様に食器であり、台がないので必ず案のような机に乗せて使う。 結婚式などでは、参列者への食物を入れる器に用いられる。 |
| 御田植祭(おたうえまつり) | その年の豊作を祈って田植え行事を模擬的に神事として行う祭り。 |
| 御旅所(おたびしょ) | 祭の神幸(神社の神様がみこしなどに乗って移動する事)の時、出御した神輿を一定の期間とどめて安置する場所。 |
| おみくじ(おみくじ) | 神社や仏閣で引かれる籤(くじ)の一種で、個人の運勢や吉凶を占うために用いられる。 「御神籤(おみくじ)」や「御仏籤(みくじ)」とも表記され、神様の意志を知る手段とされている。 |
か行/神道・神社の用語解説
| 語句 | 意味・解説 |
|---|---|
| 海宮伝説(かいきゅうでんせつ) | 日本神話に登場する、海幸彦と山幸彦という兄弟の物語のこと。 昔話で有名な浦島太郎の原型となった話といわれている。 |
| 雅楽(ががく) | 日本古来の歌舞や儀式音楽に、仏教伝来とともに中国や朝鮮半島から伝わった音楽や舞が融合し平安時代に完成したとされる日本最古の音楽芸術のこと。 宮廷音楽であり、神社における祭典用音楽ともなった。 |
| 篝火(かがりび) | 鉄製の「篝籠(かがりかご)」を同じく鉄製の三脚に乗せたり、腕竿から吊したりしたもの。 篝籠の中で薪を焚き、境内などの夜間照明に用いる。 |
| 神楽(かぐら) | 「神座(かむくら)」が語源といわれ、神をまつるために神前に奏する舞楽をいう。 神をまつるために奏する歌舞。 神道において神事の一環として行われる歌や舞のことで、神々に奉納する重要な儀式。 神様を招いてその前で行う祭りであり、「神様を祝福する」「神様とともに遊ぶ」などの意味も持っている。 |
| 神楽殿(かぐらでん) | 御神楽を奏し、祈願を行う建物。 |
| 賢所(かしこどころ) | 「けんしょ」とも読む。 宮中三殿の内のひとつで天照大御神の御霊代として神鏡が祀られている。 |
| 拍手(かしわで) | 神を拝む時に手を打ち鳴らすこと。 古来の最高の敬礼作法。拍手のこと。 手へんが木へんと間違えられてこのような呼び名になったといわれている。 正しい柏手の打ち方としては、両手の平を合わせたのち、右手を2~3cm引いてずらしてから打つ。あまり大きな音をたてる必要はない。 神宮では8回、出雲大社では4回手を打ち鳴らすが、一般の神社では2礼2拍手1礼となっている。 |
| 堅魚木(かつおぎ) | 「勝男木」、「葛緒木」とも書く。 神社の屋根の上に千木と併用される短い水平材。 後世では神社の尊厳を示す装飾的な意味合いが強いが、元来は建物の補強材であった。 |
| 神棚(かみだな) | 自宅で大神宮や氏神などの神符をまつるための棚。 |
| 惟神(かむながら) | 奈良時代まで用いられていた古語。 「神の御心のままに」、「神そのままに」といった意味で使われていた。 |
| 土 器(かわらけ) | 素焼きの焼き物の総称であるが、主として神酒を注いで飲むための小さな皿を指して言うことが多い。 伊勢神宮では、現在も神様のお食事は土器に盛りつけている。 |
| 官祭招魂社(かんさいしょうこんしゃ) | 今の護國神社のこと。 国に殉じた者や戦死者を合祀した神社。戦死した者の御霊と祀っている。 |
| 勧請(かんじょう) | 神様の分霊を迎えること。 離れた場所にいる神や仏に対して、こちらへ来てくれるように祈り願うことを意味する。 |
| 勧請神(かんじょうしん) | 本祀の神社の祭神の分霊を迎えて、新たに設けた社殿に鎮祭した神をいう。 |
| 神嘗祭(かんなめさい) | 伊勢神宮で秋に行われる最重要儀式。 その年に穫れた新穀を内宮、外宮にお供えする祭典。宮中祭祀のひとつ。大祭。 五穀豊穣の感謝祭にあたり、宮中および神宮(伊勢神宮)で儀式が行われる。 また、祝祭日の一つで、秋の季語でもある。 |
| 神主(かんぬし) | 神社に仕えて神をまつる人。 |
| 官幣社(かんぺいしゃ) | 古代の神社の制度で神祇官(官僚組織)から祈年祭、月次祭(6月、12月)、新嘗祭にお供え物を奉納される神社のこと。 一定の社格を持つ神社に奉納される。 明治以後には皇室から提供された。 第二次世界大戦以降、神社が国家管理から離れるとともに、この制度は廃止となった。 |
| 記 紀(きき) | 古事記と日本書紀のこと。 |
| 紀元祭(きげんさい) | 日本の建国を記念する祭祀。 神武天皇が即位した日。 神武天皇の大業を偉業を称え、国民の安寧、国家の隆昌、世界平和を祈念する祭。 |
| 忌 中(きちゅう) | 家族が死んだ時,家人が慎んでいる期間。 特に、死者が宙をさまよっているといわれる死後49日間のこと。 |
| 吉 兆(きっちょう) | 福笹(笹の枝)につける縁起物のこと。 福笹につける「吉兆」は銭袋、打出の小槌、あわびのし、大福帳、小判、米俵、鯛などで野、山、海それぞれの幸を象徴しています。 家内安全、開運承服、商売繁盛を祈願する意味もある。 また、よいことが起こる前兆のことでもある。 |
| 祈 禱(きとう) | 神仏にその加護・恵みを求めて祈ること。 また、その祈り。 |
| 祈年祭(きねんさい) | 「としごいのまつり」とも呼ばれる。旧暦2月4日、五穀豊穣などを願って行なった祭り。 民間でも行なった。改暦以降は2月17日となっている。 |
| 旧辞(きゅうじ) | 古事記より以前に存在したといわれる日本の歴史書のひとつ。 |
| 宮中三殿(きゅうちゅうさんでん) | 宮中にある賢所、皇霊殿、神殿の総称。 |
| 教派神道(きょうはしんとう) | 明治時代に政府によって公認された神道系の宗教団体の総称。 教派神道13派とも言い、出雲大社教、御嶽教、黒住教、金光教、實行教、神習教、神道修成派、神道大教、神理教、扶桑教、禊教、大成教、天理教の13派をいう。 |
| 教部省(きょうぶしょう) | 明治時代に設置された神道や仏教などの宗教に関する事務管理を担っていた中央官庁組織。 |
| 禁忌(きんき) | 一般的には「タブー」とも呼ばれ、道徳的、文化的、宗教的な理由で行ってはならないことを意味する。 神道においては、死・病気・血など不浄なものが禁忌とされている。 |
| 禁足地(きんそくち) | 歴史や宗教的な背景から、一般人の立ち入りが禁止されている場所を指します。 伝承や神話に基づき、特定の人々のみが入ることを許される場合もある。 |
| 宮司(ぐうじ) | 神社の最高責任者。 神社の長として、祭祀や社務を管理している。 宮司は各神社に1人。 神社の役職は順に宮司以下、権宮司、禰宜、権禰宜、九条、出仕となっている。 |
| 百済(くだら) | 古代の朝鮮半島南西部にあった国家。 |
| 国津神(くにつかみ) | 日本神話における神々の種類で、主に地上に存在する神様のこと。 古代から日本列島に土着していた神様とされ、自然や地域の守り神として崇拝されている。山・川・海など自然を司る存在とされていることが多い。島根県の出雲大社に祀られているオオクニヌシが代表的。 天津神に対して称される。天孫降臨以前からこの国土に住み、その土地を守護する神およびその子孫。 |
| 国造(くにのみやつこ) | 古代日本の行政機構において地方を治める官職のこと。 |
| 熊襲(くまそ) | 南九州のこと。または、そこに住む人。 |
| 久米歌(くめうた) | 神武天皇が東征で勝利した時に久米部の兵たちが詠った軍歌。 |
| 境内(けいだい) | 神社や寺院の敷地内のこと。 神聖な場所としての意味合いが強く、他の土地と区別されている。 境内の造りは様々であるが、基本的には鳥居・手水舎・拝殿・本殿などが配置されている。 |
| 穢れ(けがれ) | 汚れや不浄を意味するもの。 神道においては死・病気・血などが穢れとされ、塩をまく・水で洗う・火で焼くなどによって祓う。 人間の死や生、出産に関する不浄のこともいう。死の穢れは主に塩によって祓い清められる。 「ケ」が枯れる「ケガレ」から転化した言葉といわれています。 |
| 献詠祭(けんえいさい) | 和歌を詠んで神社を奉る祭りのこと。住吉大社では「新年献詠祭」、「松苗神事」、「観月祭」と年三回にわたって献詠祭が行われている。 |
| 元始祭(げんしさい) | 宮中の三殿で、正月3日、天皇自ら天皇の位の元始を寿ぐ祭典。神社においても行う。 |
| 献幣使(けんぺいし) | 神社本庁から神社の例祭等にお供えもの(供物)をする使者のこと。 |
| 兼務社(けんむしゃ) | 神職が本務の神社以外の神社を兼務する場合、その社を「兼務社」という。 |
| 高句麗(こうくり) | 古代の中国東北部南部から朝鮮北中部周辺にあった国家。 |
| 合祀(ごうし) | 神社の祭神を他の神社に合わせ祀ること。 またその祭祀を合祀祭という。 |
| 郷社(ごうしゃ) | 戦前の神社社格のひとつ。 府県社の下、村社の上に位する。 |
| 皇霊殿(こうれいでん) | 宮中三殿のひとつ。 歴代の天皇や皇族の霊を祀っている。 |
| 国幣社(こくへいしゃ) | 各地の国司より幣帛(お供え物、供物)を奉る神社。 明治に入り国庫より幣帛がささげられるようになった。 |
| 胡床(こしょう) | 主に拝殿で用いる折り畳み式の簡易椅子。 床几(しょうぎ)、合引(あいびき)とも呼ぶ。 |
| 御神体(ごしんたい) | 神道において神が宿るとされる物体で礼拝の対象となるもの。 御神体は神そのものではなく、神霊が宿ることで初めて神様になるものとされ、依代(よりしろ)とも呼ばれる。 |
| 御神木(ごしんぼく) | 神道において、特別に神聖視される樹木のこと。 神社の境内やその周囲に存在することが多い。 神様の依り代として崇められているものや、この世と神域の境に結界として立っているものなどがある。 |
| 国家神道(こっかしんとう) | 国家の支援や天皇制を支えるために利用された国家管理下の神道を広く指す。 第二次世界大戦後、GHQの神道指令によって解体される。 |
| 別天つ神(ことあまつかみ) | 日本神話で一番最初に生まれた5柱。 |
| 言霊(ことだま) | 言葉に宿る霊的な力や影響のこと。 言語にこもる精霊、またその威力。 我が国にあっては、神々や貴人の発する詞が聖詞・賀詞として保持され威力を発揮した。 この聖なる詞は祝詞(のりと)、寿詞(よごと)、呪言(とこひ)、唱言(となえごと)、語事(かたりごと)等と呼ばれている。 日本では古来より言葉には特別な力があると信じられている。 発せられた言葉は現実に影響を与えるとされている。 |
| 御幣(ごへい) | 神道の祭祀で用いられる神祭用具のひとつ。 幣帛(供物)の一種。白色や金色の紙または布を切り、細長い木にはさんで垂らしたもの。 |
| 狛犬(こまいぬ) | 神社の入口や本殿の前に、一対で設置される獣の像。邪気を祓い、神前を守護する役割を担う。 ライオンを基に形象化されたもので、初めは犬に似ていたが平安末期に獅子に近い形になった。向かって右側が口を開けた「阿形(あぎょう)」、左側が口を閉じた「吽形(うんぎょう)」として配置されるのが一般的。 獅子の形状をしたものが多いが、狐・狼・兎・シーサーの狛犬がある神社もある。 |
| 薦(こも) | 藁(わら)で荒く編んだ筵(むしろ)。 地面や床とお供え物などを隔離するためのもので、通常は案の下に敷く。 |
| 権現神(ごんげんしん) | 仏がその身を隠し、人間を始めすべての生物を救うために仮の姿で現れた神。 |
| 権禰宜(ごんねぎ) | 宮司、禰宜の命を受け社務に従事する神職。 権禰宜以上を神職という。 |
さ行/神道・神社の用語解説
| 語句 | 意味・解説 |
|---|---|
| 斎王(さいおう) | 天皇の代わりに伊勢神宮で奉仕した未婚の皇族女性。 |
| 祭祀(さいし) | 神々や祖先などをまつること。 宗教的な背景を持ち、感謝・祈願・鎮魂などの意を込めて行われる儀式や行事のこと。 |
| 斎主(さいしゅ) | そのお祭りを斎行している主たる(祝詞を奏上する)神職。 それ以外の神職は斎員(さいいん)と呼ぶ。 |
| 祭神(さいじん) | 神社にお祀りされている神。 神社に主として祀ってある神を主祭神という。 相殿として配祀神を祀ってある場合もある。 |
| 祭政一致(さいせいいっち) | 祭祀と政治が一体化している状態のこと。 祭祀者が政治の中心者を兼ねていた古代社会に多く見られた。 邪馬台国の卑弥呼や、琉球王国の聞得大君(きこえおおきみ)などが有名。 |
| 歳旦祭(さいたんさい) | 新年を祝い、御賀の寿詞を奏し、皇室の弥栄と国家の隆昌を祈念する祭祀。 |
| 榊(さかき) | 聖域との「境(さかい)に植える木」で「さかき」と呼ぶ。 常緑のため「栄える木」が縮まって「さかき」とされることもある。 |
| 里宮(さとみや) | 山麓にまつられている神社のことで、奥宮に対していわれる。 |
| 山岳信仰(さんがくしんこう) | 山そのものを神体としたり、山に祖霊が住むとして、霊山として崇拝すること。 |
| 三種神器(さんしゅのしんき) | 三種神宝ともいう。 皇孫瓊瓊杵尊が天照大御神と高御産霊神から葦原中国の統治の勅命を受け、高天原を出発するにあたって、大神の皇孫に授けられた八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)、八咫鏡(やたのかがみ)、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)〔又は草薙剣(くさなぎのつるぎ)とも言う〕の3つの神宝を指す。 |
| 参 道(さんどう) | 社寺に参詣するための道のこと。 初めの鳥居をくぐって社殿までの道を指す。 参道の中央は正中と呼ばれる神の通り道であり、参拝のときには真中を避けて端を歩くことが礼儀とされている。 |
| 三 方(さんぼう) | 神様に神饌をお供えするときなどに使用する食器の一種。 3方向に象眼のある台の上に隅切りの折敷(すみきりのおしき)を乗せたもの。 |
| 潮乾珠(しおふるたま) | 日本神話に登場する珠。 海水を干上がらせ海を陸地に変える力を持つとされている。 |
| 潮盈珠(しおみつたま) | 日本神話に登場する珠。 海水満ちさせ陸地を海に変える力を持つとされている。 |
| 式外社(しきげしゃ) | 式内社に対し、それ以外の神社をいう。 延喜式神名帳に記載されていない神社のこと。 平安時代における神社の数は約3万社であったが、その内から式内社2861所を除いた神社。 |
| 式内社(しきないしゃ) | 延喜式にその名が記述されている神社。 全部で2861社ある。これに名があるということは、その当時すでに国家によってその存在を認められていたことを意味する。 延喜式内社のことで、延喜式神名帳(じんみょうちょう)に書かれた官社(国家が祭祀した神社)をいう。 |
| 式年祭(しきねんさい) | 「式」は「さだめ」の意で、特定の定められた年数ごとに行われる祭祀。 神道における年期法要のこと。(仏教にあたる法事に相当する) |
| 式年遷宮(しきねんせんぐう) | 一定の年限をもって社殿をつくりかえ、旧殿の神儀を新殿に遷す儀式行事。 |
| 寺社奉行(じしゃぶぎょう) | 江戸幕府の役職の一つ。 寺社や僧侶、神官、寺社領などを管轄する役職。 宗教行政機関。 |
| 七五三(しちごさん) | 子供の成長を祝う年中行事。 寺社で報告、感謝、祈願を行う。 男は数え年の3歳と5歳、女は3歳と7歳の11月15日に、着飾って神社へ参詣する習俗。 三才を髪置、五才を袴着、七才を帯解という。 |
| 地鎮祭(じちんさい) | 地祭(じまつり)ともいい、土木、建築を行う際に、その土地を治めている神に工事の安全と建物の無事を祈願する祭儀。 土地の神を鎮め、土地を利用させてもらうことの許しを得る祭儀であり、建築などで工事を始める前に行う。 土地の四隅に青竹などを差し、その間を注連縄(しめなわ)で結ぶなどの結界を作り、執り行う。 神を祀って工事の無事を祈る儀式と認識されており、安全祈願祭、土祭り、地祭り、地祝いと言われる場合がある。 |
| 紙垂(しで) | 注連縄(しめなわ)や玉串、竹などにつける和紙でできた飾りのようなもの。 総称として御幣(ごへい)と呼ぶこともある。 神聖な場であることを示し邪気を払う意味合いがある。 |
| 注連縄(しめなわ) | 神道における神聖な区域を示すための縄。 神前や神事の場にめぐらせて、神聖な場所と不浄な外界とを区別するための縄。 紙垂(しで)と呼ばれる白い紙飾りが付けられている。 神社の拝殿や神棚に用いられ、神域と現世を区分する役割や神様が宿るご神体をお守りする役割がある。 正月には一般家庭の玄関などにも飾られる。松葉を差して松飾りとする場合もある。 |
| 標柱(しめばしら) | 神社又は祭場の設備の一種。 参道の入口或いは社頭に建つ一対の柱で、これに「注連縄」を張る。石柱の場合が多い。 |
| 社格(しゃかく) | 神社についての等級・格式。 明治以降終戦後までは官幣大・中・小社、国幣大・中・小社、別格官幣社、府県社、郷社、村社、社格の無い神社(無格社)に分けられたが、終戦後廃止された。 |
| 笏(しゃく) | 神拝のさいに神職や光家が持つ檜や一位、桐、象牙などで作られた細長い板。 威儀を示すための持ち物といて用いられていた。 |
| 社家(しゃけ) | 世襲(特定の地位や職業、財産などを子孫が代々受け継ぐこと)の神職の家柄をいう。 明治4年世襲制は廃止になったが、出雲大社や阿蘇神社など現在も続いている神社もある。 |
| 社号(しゃごう) | 神社の称号。 神宮、○○宮、○○大社、○○神社、○○社、○○大神宮の7種ある。 |
| 社寺局(しゃじきょく) | 教部省が廃止された後に、内務省に置かれ、神社、寺院の行政を管轄した中央官庁。 明治33年に神社局と宗教局の二つに分けられた。 |
| 社僧(しゃそう) | 神社あるいは神社の神宮寺に所属し、神祇のために僧形をもって仏事を執り行っていた者の称。 奈良時代からの神仏習合傾向により、神宮寺を置く神社が多くなり、中には社僧が神職の上位に立って一社を支配するようなところもあった。 明治になって廃止された。 |
| 社日(しゃにち) | 春分、秋分に最も近い戊(つちのえ)の日をいう。 土地の神様を司る日であり日本では特に農作儀礼として重要視されてきた。 春は豊作、秋は収穫に感謝する行事が行われる。 |
| 社務所(しゃむしょ) | 神社の事務一般を取り扱う場所。 |
| 社領(しゃりょう) | 神社の領地。神領ともいう。 |
| 儒教(じゅきょう) | 紀元前の中国に起源を持つ、孔子を始祖とする思想・信仰の体系。 西暦400~500年頃に日本に伝わったとされ、神道にも大きな影響を与えている。 |
| 修験道(しゅげんどう) | 日本古来の山岳信仰に、仏教や神道の要素が融合した独自の信仰形態。 山に籠もって厳しい修行を行うことで神秘的な力を得て、自他の救済を目指すことを主な目的としている。実践者は「修験者(しゅげんじゃ)」や「山伏(やまぶし)」と呼ばれる。 山岳で修行をして霊験を悟ろうとする仏教の一派であるが、神仏習合の影響を受けて神道と深い関係を持つ。 |
| 主祭神(しゅさいじん) | 神社の主体としてまつる神。 |
| 修 祓(しゅばつ) | 神道における儀式の一つで心身を清めるためのお祓いを意味する。 祭典において神様をお招きする前のお祓いの事。 |
| 殉死(じゅんし) | 古代で主君が亡くなった時に、お墓に一緒に埋まること。垂仁の時代に禁止される。 |
| 小祭(しょうさい) | 大祭、中祭以外の祭祀で、小祭式で行う祭祀のこと。 |
| 上棟祭(じょうとうさい) | 建物の建築の際、柱や梁を組み立ててその上に棟木(むなぎ)を上げることで、この時に家屋の守護神をまつって建物の安全と幸運を祈願する祭祀。 |
| 新羅(しらぎ) | 古代の朝鮮半島南東部にあった国家。 |
| 神苑(しんえん) | 直接神社の宗教的関係ある本殿や摂末社、社務所或いはお旅所等がある地域と、これに接続する苑地や林地の一帯。 |
| 神階(しんかい) | 古代日本において調停が神社の祭神に授けた位階の事。神祇に奉った位。 神階には位階、勲位、品位の三種があった。 |
| 神官(しんかん) | 社格ある神社に奉仕する官吏の身分を与えられた職員の事を指したが、現在は神職と呼び神官は使用しない。 |
| 神祇院(じんぎいん) | 神社局を廃しておかれた。 神祇行政を管掌した中央官庁。 内務大臣の管理に属し、伊勢神宮、官国幣社以下神社のこと、神官及び神職のこと、敬神思想の普及に関することをつかさどった。 |
| 神祇官(じんぎかん) | 神祇行政を管轄した中央官庁。 |
| 神宮(じんぐう) | 伊勢神宮の正式名称。明治神宮、熱田神宮等と区別するため一般には伊勢神宮という。 |
| 神宮寺(じんぐうじ) | 神社に付属しておかれた寺院で、神仏習合の現れである。 神宮院、宮寺、神願寺、神護寺、神供寺などの別称がある。明治になって神仏分離により、神社から分離又は廃絶した。 |
| 神庫(しんこ) | 御祭神のお使いになる御神宝類を収容する倉庫。 |
| 神号(しんごう) | 神々の名前を尊称して付ける称号。 古代においては「尊(みこと)」、「命(みこと)」が、神仏習合時代には、「明神(みょうじん)」、「大菩薩」、「権現」が成立した。 |
| 神幸祭(しんこうさい) | 神が神輿等に乗って本殿から別の場所へ移動する神事のこと。 |
| 神使(しんし) | 神道において、神の使者や眷属とされる特定の動物のこと。 神の意志を伝えたり、神と人間との接触を媒介する役割を果たす。 神の使いと考えられている鳥獣虫魚のこと。 春日・鹿島・厳島の鹿、日吉・春日の猿、熊野・住吉の烏など。 神使は一般的に祀られている神様に縁のある動物であり、稲荷神社の狐や春日大社の鹿などが有名。 |
| 神社局(じんじゃきょく) | 内務省にあった1局で、神社行政の中央官庁。明治33年に社寺局を分けて神社局と神社以外の宗教を所管する宗教局とした。 昭和15年神社局を廃し、内務省の外局として神祇院が設置された。 |
| 神社神道(じんじゃしんとう) | 氏神や産土神を始め、天皇、皇族、偉人、義士烈士、戦没者などを神としてまつる施設を中心として、これに伴う祭祀儀礼を含んだ信仰組織の総称。 |
| 神社本庁(じんじゃほんちょう) | 宗教法人として昭和22年に設立された全国約8万社を包括する宗教団体。 東京都渋谷区代々木にあり、地方機関として全国の都道府県に神社庁を置く。 |
| 神職(しんしょく) | 神社の職員のうち、宮司、権宮司、禰宜、権禰宜相当以上の者をいう。 |
| 神饌(しんせん) | 神様へのお供え物。 本来はそのまま食べていただける食物や飲み物(お酒など)を指すが、お金を神饌としてお供えすることも多い(神饌料) |
| 神饌田(しんせんでん) | 神田、宮田、御供田ともいう。 神に属し祭祀に供せられる稲を作る田。 |
| 神葬祭(しんそうさい) | 神道式の葬祭(お葬式)のこと。 通夜祭(神式のお通夜のこと)から始まって、いくつものお祭りが行われるが、それらを総称してこのように呼ぶことが多い。 |
| 神託(しんたく) | 神のお告げ。 託宣(たくせん)ともいい、神が人または物に憑依し、或いは夢に託して神意をお知らせになること。その状態になることを神懸かりという。 |
| 神勅(しんちょく) | 神が下した言葉。 特に天照大御神が天孫降臨の際に、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に下した三大神勅(天壌無窮の神勅、宝鏡奉斎の神勅、斎庭の稲穂の神勅)は歴代天皇が受け継ぐものとして最重要視されている。 |
| 神典(しんてん) | 古事記、日本書紀、古語拾遺、宣命、令義解、律、延喜式、新撰姓氏録、風土記、万葉集を収載した書籍。 |
| 神殿(しんでん) | 御神体の安置されている社。 基本的にはひとつの建物として独立している。 宮中三殿の一つ。神社の本殿を指す場合もある。 |
| 神道(しんとう) | 特定の開祖や教典を持たず、自然や人間の生活に密接に関連した日本独自の信仰体系のこと。 森羅万象に神が宿るというアニミズム的な思想に基づいており、八百万の神々を信仰対象としている。 |
| 神道指令(しんとうしれい) | GHQによる神道指令(国家神道と神社神道を分離し政治と宗教 を分離することを目的とした覚書)が発令され国家神道は解体される。 国家による神社への特別な保護は禁止され、神社は宗教法人として自立することを求められる。 この時に、神道は他の宗教と同様に私的な信仰、民間信仰として再出発することになる。 |
| 神徳(しんとく) | 神の功徳、威徳のことで、その神の神業によって霊験がある事柄。 |
| 神符(しんぷ) | 神社から氏子、崇敬者へ授与する信仰の対象物としてのお札。 |
| 神仏習合(しんぶつしゅうごう) | 日本の神道信仰と仏教信仰が融合し、調和した宗教形態のこと。 特に平安時代後期に大きく発展し、神道と仏教の教義や実践が互いに影響を与え合う形で形成され、明治時代の神仏分離令まで続きました。 |
| 神仏分離(しんぶつぶんり) | 明治元年、千有余年に亘って行われて来た神仏習合を禁止し、両者を分離した行政方策。 明治初期に行われた、神道と仏教を明確に区別することを目的とする宗教政策。 神仏習合の慣習を禁止し、神道を国教化するために行われた。 神社から仏教的要素が排除され、仏教弾圧の風潮を生んだ。 |
| 神宝(しんぽう) | 祭神の料として本殿の内に奉安するするもの。 刀剣、鏡、武具、衣料等多岐にわたる。 |
| 神馬(しんめ) | 神の乗用に供する馬の意で、神社に奉納した馬。 |
| 神紋(しんもん) | 神社の紋章。装飾用等に用いる。 |
| 神輿庫(しんよこ) | 神輿を格納するところ。 |
| 神話(しんわ) | 「古事記」、「日本書紀」、「風土記」、「古語拾遺」などの上代古典に見える神々の物語を呼び、天皇の祖神を中心とした日本人の祖先の歴史。 |
| 水神(すいじん) | 飲料水や水稲耕作に必要な水をつかさどる神。川・井戸・泉などのほとりにまつられる一方、蛇・河童・竜などの姿で表される。 |
| 随神門(ずいしんもん) | 随身とも書く。神域に邪悪なものが入り来るのを防ぐ御門の神をまつる門。 |
| 崇敬者(すうけいしゃ) | 氏子区域に居住する氏子と違って、その居住区域に関係なく何らかの信仰的契機により、その神社を継続的に崇敬する人をいう。 |
| 主基(すき) | 大嘗祭(だいじょうさい)に定められている2つの祭祀のそれぞれの一方の系列に関する名称。 新穀を奉るための二つの国のうちの一つ。 東側を「悠基国」(ゆきこく)、西側を「主基国」(すきこく)と呼ぶ。 |
| 正史(せいし) | 国が正式にまとめた歴史書のこと。 |
| 精霊(せいれい) | 物質的な身体をもたないが、ある種の個性を備えた超自然的存在や力。 草木河川等に宿るとされる。 |
| 摂社(せっしゃ) | 神社の本社に付属し、その祭神と縁の深い神様を祀った神社のこと。 摂社は御子神(みこがみ)・荒御魂(あらみたま)・地主神(じぬしがみ)など由緒ある神様を祀ることが多く、末社よりも格式が高いとされている。 |
| 遷宮(せんぐう) | 神社の本殿を改築または修理する際に、御神体を新しい本殿に移す儀式のこと。 神殿を定期的に新しくすることで、神様の力を再生させる重要な意味がある。 伊勢神宮において20年ごと、出雲大社において60年ごとに行われる式年遷宮が有名。 |
| 遷座祭(せんざさい) | 神霊を本殿から仮殿へ、または仮殿から本殿へ遷す祭祀で、前者を仮殿遷座祭、後者を本殿遷座祭という。 |
| 宣命(せんみょう) | 天皇の勅命を書いた文書のうち、国文体で書かれたもの。 |
| 総社(そうじゃ) | 平安時代に国司の巡拝の制が衰えた時に、参拝の煩わしさを省くために国庁近く、又は便宜の地に管内の神社の祭神を合祀し、参拝する為の神社。 |
| 総代(そうだい) | 神社の運営について役員を助け、宮司に協力する神社機関の一員。氏子、崇敬者の世話や祭典、その他の執行にあたり宮司に協力するが、法律的な権利や権限を有しない。 |
| 外削ぎ(そとそぎ) | 千木(ちぎ=神社の建築にみられる屋根の両端にある交差した装飾。木材。)の先端が垂直に切られた形状。 伊勢神宮の外宮が外削ぎ。 |
| 祖霊社(それいしゃ) | 先祖累代の霊をまつる社。 明治に入り氏神の境内に氏子の人々の霊をまつり祖霊社とした。 |
| 祖霊崇拝(それいすうはい) | 亡くなった先祖の霊が、生きている子孫に影響を与えると信じる信仰のこと。 日本では弥生時代には自然発生していたと考えられており、神道においても重要な考え方のひとつ。 「先祖祭祀(せんぞさいし)」「祖先崇拝(そせんすうはい)」「祖霊信仰(それいしんこう)」とも呼ばれる。 |
| 村社(そんしゃ) | 戦前の神社社格の一つ。郷社の下に位する。 |
た行/神道・神社の用語解説
| 語句 | 意味・解説 |
|---|---|
| 大祭(たいさい) | 神社祭祀の区分の一つで、大祭式をもって行う祭祀のこと。 主に例祭、祈年祭、新嘗祭、式年祭、鎮座祭、遷座祭、合祀祭、分祀祭をいう。 |
| 大嘗祭(だいじょうさい) | 天皇が即位後に初めておこなわれる「新嘗祭」のこと。「おおにえのまつり」ともいう。 大嘗とはもともと神に奉る食料や衣料のことを表しており、この祭りではその年の新穀を献じて天照大神や天神地祗(神々の総称)を祭る神事でも最大級のもの。 |
| 高千穂(たかちほ) | ニニギノミコトが高天原から葦原中国の最初に降りたった場所。 |
| 高天原(たかまがはら) | 日本神話における神々が住む天上の世界のこと。 アマテラスが治めており、古事記や祝詞にその名が登場する。 地上界の「葦原中国」、地下界の「根の国」対して使われる。 |
| 山車(だし) | お祭りのときに様々な飾り物をつけて担いだりする車の台車。 「だんじり」とも言う。 本来は神さまの宿っている御幣や花、榊、竹の籠などを言った。 |
| 玉 垣(たまがき) | 一般の神社では、神社境内と外界との間に設けられた垣根のこと。 鳥居の両脇から伸びていることが多く、材質は御影石など。 奉納者の氏名が彫ってあることが多い。 |
| 玉 串(たまぐし) | 榊の枝に紙垂(しで)を結びつけたもの。 神様の御霊と参拝者の魂を繋ぐものという意味で玉(魂)串(ものをつなぐ)と呼ぶ。 参拝者や神職が神前に捧げることで、災いから守ってもらえると信じられている。 |
| 千木(ちぎ) | 本殿の屋根等で交叉した木。 破風が延びて交わった構造的なものと、棟上に跨がらせた置き千木がある。 もとは構造的なものであったが、神社の象徴として用いられるようになった。 内削ぎと外削ぎとがある。 |
| 稚児(ちご) | 神社・寺院の祭礼・法会(ほうえ)などで、天童に扮して行列に出る男女児。 公家・神社・寺院などに召し使われた少年。 赤ん坊、幼児、子供の意味もある。 |
| 中祭(ちゅうさい) | 神社祭祀の区分の一つで、中祭式をもって行う祭祀のこと。 主に歳旦祭、元始祭、紀元祭、昭和祭、神嘗奉祝祭、明治祭、天長祭をいう。 |
| 手水舎(ちょうずや、てみずや) | 神社で参拝前に手や口を清めるための場所。 参道の入り口や社殿の脇に設置され、水盤(すいばん)と柄杓(ひしゃく)が備えられている。 手水舎での清めは、心身を清らかにして神聖な場にふさわしい状態に整える意味がある。 |
| 勅祭社(ちょくさいしゃ) | 天皇のお使いである勅使が参向して祭祀が執行される神社。 |
| 勅使(ちょくし) | 天皇の命を伝える使者。 |
| 鎮魂(ちんこん) | 死者の魂をなぐさめ、しずめること。 |
| 鎮座(ちんざ) | 神霊がある場所にしずまりとどまっていること。 |
| 鎮座祭(ちんざさい) | 浄地を選んで社殿を建立し、神霊を鎮めまつる祭祀。 |
| 鎮座地(ちんざち) | 神社の住所のことで、主たる事務所の所在地を指す。 境内に社務所がある場合は、社務所のある地番、社務所の無い場合は、本殿のある地番とする。 |
| 鎮守(ちんじゅ) | 一定の地域・建造物などを守護するために祀られた神。 土着の神をしずめて,国・城・寺院・村落などを守護する神。 近世以降、氏神・産土神・地主神などと同一視し、各村落の神社をさすようになった。 |
| 追儺(ついな) | 中国から伝来した疫鬼を追う行事。 後世では節分の夜、豆を撒いて災いを追い払う行事となった。 |
| 月次祭(つきなみさい) | 毎月決まった日に神社で行われる祭典の事。 氏子や崇拝者は神様からのご加護に感謝して今後の無事を祈る。開運承服、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、健康長寿を祈願する。 |
| 土雲(つちぐも) | 古代日本においてヤマト王政に服従しなかった土着の豪族や集団を指す言葉。 |
| 帝紀(ていき) | 歴代の天皇あるいは皇室の系譜。 古事記より前にあった日本の歴史書。 |
| 撤 饌(てっせん) | 神饌をご神前から下げたもの。 俗に言う「神様のおさがり」である。 |
| 天孫降臨(てんそんこうりん) | 天照大御神の御孫、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が大神の命令で高天原から葦原中国(日本)へ降りられたことをいう。 |
| 天長祭(てんちょうさい) | 天皇の御誕生日にあったって、国民が慶祝の意を表し、神祇に感謝し、聖寿の万歳と国家の長久を祈念する祭祀。 |
| 杜氏(とうじ) | 日本酒の酒造りにおける最高責任者のことです。 蔵人(くらびと)を指揮し、酒造りの全工程を管理・監督する役割を担う。 |
| 東征(とうせい) | 東方へ征伐しに行くこと。 |
| 当屋(とうや) | 神社の祭礼や講の行事にあたってその中心となる人又はその家。 |
| 燈籠(とうろう) | 神様に「明かり」をお供えするためのものを特に御神灯と呼ぶ。 石灯籠・吊り灯籠・外陣灯籠などの種類があり、氏子崇敬者の寄進で設けられることが多い。 |
| 常世の国(とこよのくに) | 古代人が海の向こうの遠いところにあると考えていた祖先の霊と神々が住むの理想の国。 |
| 歳神(としがみ) | 正月に家にやってくる神。 歳徳神、正月様ともいう。 |
| 鳥居(とりい) | 神社の参道入口などに立てて神域を示す一種の門。 神域の表示あるいは神社の門などとして建設する特殊建築。独立して建てられ、神域を表示する場合も多いが、発達の次第からみると垣(玉垣)や塀の間に設けた門柱としてできたものが様式化された。 伊勢神宮や鹿島神宮の神明鳥居を基本とし、明神鳥居・春日鳥居・山王鳥居・稲荷鳥居・三輪鳥居・両部鳥居など種々の様式がある。 木製が本式だが石製・青銅製・鉄製・陶製もあり、近年では鉄筋コンクリート製もある。 |
な行/神道・神社の用語解説
| 語句 | 意味・解説 |
|---|---|
| 内陣(ないじん) | 神社の本殿の奥にあり、御神体を安置しておく場所。 |
| 直会(なおらい) | お祭りに供えたものを撤下して食べる行事。 一般にはお祭りの後で行う酒食を言うが、本来は神さまのお下がりを食べてお陰をいただく行事のこと。 |
| 新嘗祭(にいなめさい) | 「しんじょうさい」ともいう。 神にその年に収穫した新穀を供えて、神恩に感謝する祭り。宮中儀式の一。 天皇が新穀を神々に供え、自身も食する。 明治6年以降は11月23日に行われ祭日とされた。 天皇の即位後初めて行うものを大嘗祭(だいじようさい)という。にいなめさい→ 勤労感謝の日。 |
| 和魂(にぎみたま) | 神道における神様の霊魂のひとつ。 穏やかで温和な霊力を表し、荒魂(あらみたま)とは対照的に柔和で調和的な性質を持っている。 日本の神様は和魂と荒魂のふたつの側面を持ち、和魂はさらに「幸魂(さきみたま)」「奇魂(くしみたま)」に分けられるとされている。 |
| 二十二社(にじゅうにしゃ) | 平安時代中期以降に朝廷の崇敬が篤い、国内神社の代表ともいうべき神社が22あり、特別の社格の神社として取り扱われた。 明治維新後廃止され伊勢の神宮は別格としてその他は、官幣大社、中社に列格された。 |
| 幣(ぬさ) | 神に捧げる供え物。 また,祓(はらえ)の料とするもの。 古くは麻・木綿(ゆう)などを用い,のちには織った布や紙を用いた。 幣帛(へいはく)。御幣(ごへい)。 |
| 禰宜(ねぎ) | 宮司の命を受け社務に従事する神職。 宮司の補佐役。 宮司、権宮司に次ぐ神職の役職名。 |
| 根の堅洲国(ねのかたすくに) | 根の国とも呼ばれる。 黄泉平坂の先にある地下の国。 黄泉の国とは異なり再生の意識や魂の存在が繋がれる位置。 |
| 能褒野(のぼの) | 三重県亀山市付近。 ヤマトタケルが亡くなった場所。 |
| 祝 詞(のりと) | 神道の祭祀において、神職が神様に対して唱える言葉。 祝詞は古体の独特な文体を持ち、言霊の力で罪や穢れを祓うと信じられている。 神事に際し,神前で読み上げて神に申し請う内容・形式の文章。 現存する最も古いものは「延喜式」に収められた「祈年祭(としごいのまつり)」以下の二七編。 今日でも神事に奏される。文末を「…と宣(の)る」で結ぶ宣命形式のものと「…と申す」で結ぶ奏上形式のものとがある。 |
| 祝詞殿(のりとでん) | 祝詞を奏上する建物。 |
は行/神道・神社の用語解説
| 語句 | 意味・解説 |
|---|---|
| 拝 殿(はいでん) | 神殿に向かって参拝者が拝礼する屋根付きの場所。 神社の建物群の一部で、参拝者が神様に拝礼するための場所です。通常、本殿の前に位置し、賽銭箱が置かれていることが多い。 拝殿は神職が祭典を行う場でもあり、参拝者はここで神を拝み祈願を行う。 拝殿と本殿は混同されがちですが、本殿が神様を祀るための建物であるのに対し、拝殿は参拝者のための建物。 |
| 拝 礼(はいれい) | 心を込めた深いお辞儀。 上半身が床と水平になるまで深く頭を下げる。 立って拝礼する場合は、腰の角度が約90度になるまで頭を下げる。 |
| 白拍子(はくびょうし) | 平安末期におこった歌舞のことです。 |
| 初午(はつうま) | 2月最初の午の日をいい、稲荷神社では初午祭や稲荷講が営まれる。 稲荷神が降臨した日が初午の日であったという伝承に由来する。 |
| 初宮詣(はつみやもうで) | 誕生後初めて氏神へ参拝すること。 子の幸せな成長を祈るとともに新しい氏子として認めてもらう行事。 |
| 埴輪(はにわ) | 日本の古墳時代に特有の素焼の焼き物。 垂仁が殉職を禁止したため、代わりに埴輪を飾ることとした。 |
| 隼人(はやと) | 九州地方の民族。元祖は海幸彦。 |
| 祓(はらい) | 神に祈って罪・けがれ,災禍などを除き去ること。 また,そのための儀式や,その祈りの言葉。おはらい。 |
| 祓え(はらえ) | 神道における宗教行為で、罪・穢れ・災厄などの不浄を心身から取り除くための神事。 |
| 斐伊川(ひいがわ) | スサノオがクシナダヒメと出会った川。 ヤマトタケルがイヅモタケルと一緒に沐浴した川。 |
| 軾(ひざつき) | 神職や参拝者が座るための正方形の二辺のみ縁付きの茣蓙。 |
| 聖帝(ひじりのみかど) | 仁徳のこと。 |
| 人形(ひとがた) | 人の形に模して木や竹、紙等で作った形代。 神霊の依代として信仰行事に用いたり、身体から穢や厄災を移して川や海に流したりする。 |
| 比婆山(ひばやま) | イザナギがイザナミを埋葬した山。 出雲の国と伯伎の国の間にあるらしい。 |
| 日向(ひむか) | ニニギ、山幸彦(ホオリ)、アエズが住んでた場所。 |
| 神籬(ひもろぎ) | 神祭の時、清浄の地を選んで周囲に常磐木を植えて神座としたもの。 現在の形は榊に麻と紙垂を取り付け、神の降神時の依代として使用する。 |
| 福笹(ふくささ) | 例祭「えべっさん」のときに商売繁盛を祈願して、たくさんの縁起物をつけて売られている笹のこと。 福笹につける縁起物は「吉兆」と呼ばれ、神社で授与されるもの。 |
| 府県社(ふけんしゃ) | 戦前の神社社格の一つ。 府社・県社の称。官社の次、郷社の一つ上で、諸社の最上級に位する。 |
| 風土記(ふどき) | 和銅6年(713)歴史編纂の材料として諸国に命じて国々の地名の由来、産物、古伝承などを記して朝廷に提出させた地誌。 出雲の国風土記がほぼ完本として伝わる。 |
| 分祀祭(ぶんしさい) | 祭神の御霊を分けて他の所へまつる祭祀。 |
| 分社(ぶんしゃ) | 本社に対し、別に神社を創設し、その分霊をまつった神社。 |
| 分霊(ぶんれい) | 「わけみたま」ともいう。 ある神社の祭神の霊を分けて他の神社へまつること。 |
| 幣殿(へいでん) | 神饌などをお供えしてある場所。 斉主が神前で拝礼するときの場所。 通常、一般参拝者は入れない。幣帛を奉献する建物。 |
| 幣帛(へいはく) | 元々は神様にお供えした着物。 通常は大きな両垂れの紙垂のことを指すことが多いようである。 玉串に付いた紙垂も幣帛の一種で、神前に供える金銭に「玉串料」あるいは「幣帛料」と書くのはこのためである。 |
| 別宮(べつぐう) | 本社と本末関係にある神社の称号。 |
| 別当(べっとう) | 神宮寺に奉仕する社僧の長。 |
| 別表神社(べっぴょうじんじゃ) | 神社本庁において、その由緒、活動、財政等を総合した面で顕著な神社が申請により指定される。 |
| 奉幣(ほうべい) | 幣帛を神に捧げること。 |
| 鳳 輦(ほうれん) | 屋形の上に金銅の鳳凰を飾りつけた輿(こし)。 土台に二本の轅(ながえ)を通し,肩でかつぐ。 天皇専用の乗り物で晴れの儀式の行幸に用いた。 |
| 本地垂迹(ほんじすいじゃく) | 神仏習合思想のひとつ。 神道の神々が、仏教における仏や菩薩の仮の姿であるとする考え方。 神々が仏の化身として現れることで、両者が共存し信仰が深まることを目指していた。 |
| 本宗(ほんそう) | 神社本庁では伊勢神宮が古来、至高至貴の神社であるので、全国の神社の総親神として「本宗」と称え、仰ぐ。 |
| 本殿(ほんでん) | 神社の社殿のなかで、御祭神の神霊や御神体を安置するための建物。 正殿(せいでん)や宝殿(ほうでん)とも呼ばれる。 本殿は神様のための場所であり、参拝者が直接入ることはできない。 |
| 本務社(ほんむしゃ) | 兼務社に対して、主として奉仕する神社。 |
ま行/神道・神社の用語解説
| 語句 | 意味・解説 |
|---|---|
| 舞殿(まいでん) | 神の御意を慰めるために舞や神楽を奏する建物。 |
| 纒向(まきむく) | 神武が東征して都を置いた場所。 |
| 真榊(まさかき) | 社殿や祭場の装飾具。 榊に五色絹(青、黄、赤、白、紫)を垂れ、神前に向かって右には鏡と玉を掛け、左には剣を掛ける。 |
| 末社(まっしゃ) | 神社において本社に付属し、その支配を受ける小さな社を指す。 末社は神社の境内やその周辺に位置し、祭神と縁故の深い神様やその土地で祀られていた神様を祀っていることが多い。 本社に対し枝社のことで社格の一種。 摂社とともに枝社を構成するもの。 摂社以外で本社の支配を受けている小社。 |
| 御巫(みかんなぎ・みかんこ) | 神をまつる童女。 |
| 神酒(みき・しんしゅ) | 御酒(みき)とも書く。 神前にお供えしたお酒のこと。 一般的には日本酒が供えられることが多い。 |
| 御厨(みくりや) | 神饌を調理する場所や領地のこと。 |
| 巫女(みこ) | 神様に仕える女性のこと。神社においては神楽を舞う、神事に奉仕する、神職を補佐するなどの役割を担っている。 古代の巫女は祈祷・占い・口寄せなどを行い、神の意志を伝える重要な存在でした。 神に仕えて神事を行い、また、神意をうかがって神託を告げる者。 未婚の女性が多い。かんなぎ。神がかりの状態になって口寄せなどをする女性。 |
| 神輿(みこし) | 神幸の際に神霊が乗る輿。 屋根の中央に鳳凰(ほうおう)や葱花(そうか)を置き、台に何本かのかつぎ棒を通し大勢でかつぐ。 平安中期に怨霊信仰が盛んになるにつれ広く用いられるようになった。 |
| 瑞垣(みずがき) | 神社境内の中にある御神殿の周囲に設けられた垣。 聖域中の聖域を取り囲んでおり、通常、この垣より中に入ることができるのは神職のみ。 玉垣の内側に設ける垣のことで、一般には木製の垣で神殿を囲む。 |
| 禊ぎ(みそぎ) | 神道における重要な儀式で、罪や穢れを水で洗い流し、身体と心を清める行為。 通常、川や海の清らかな水を使って行われ、神聖な状態に戻ることを目的としている。 身と心の不浄を祓い去るため、主として水を用いて全身を清めることをいう。 邪念を払い、霊的・精神的に「生まれ変わる」のである。 |
| 御扉(みとびら) | 御神殿の扉のこと。大きな祭礼の時のみ開く。 開くのは必ず宮司であり御扉を開くときに木の擦れ合う大きな音が出るように作ってある。 |
| 宮座(みやざ) | 神社の祭祀を司る氏子集団の組織。 特定の家に属する者が交代で神社の祭祀を司った。 |
| 名神(みょうじん) | 「明神」とも書く。 神社の内で特に霊験の著しい神。 後世になると名神の称は用いられなくなり、専ら明神又は大明神が用いられるようになった。 |
| 民間信仰(みんかんしんこう) | 特定の教団組織や教理体系を持たず、地域共同体や日常生活に密着した信仰のことを指す。 庶民の間で伝承され、多様な形態を持つことが特徴です。 「庚申信仰」や「道祖神信仰」などが有名です。 |
| 無格社(むかくしゃ) | 社格制度において村社に至らなかった社格のない神社。 |
| 棟札(むなふだ) | 社寺の殿舎造築の上棟祭に造営修復の由来や寄進者以下関係者、工匠等の姓名、起工竣工の年月日等を記し、棟木に打ち付けて後世への記念とする木札。 |
| 明治祭(めいじさい) | 我が国を近代国家として発展させた明治天皇の聖徳大業を景仰し、益々文化を進め産業を興すことを祈念する祭祀。 |
| 殯(もがり) | 死が確立するまで喪屋に遺体を納めておく習慣。 |
| 物忌み(ものいみ) | 神事などに関係する者が、ある期間精進潔斎すること。 |
| 桃(もも) | 古代の桃の役割としては邪気を払い不老長寿の力が有ると信じられ神話にも登場する特別な果実であった。 |
や行/神道・神社の用語解説
| 語句 | 意味・解説 |
|---|---|
| 八百万の神(やおよろずのかみ) | 日本の神道における多くの神々を指す総称。 「八百」は数が極めて多いこと、「万」はさまざまであることを意味し、自然界のあらゆるものに神が宿るというアニミズム的な信仰に基づいている。 『古事記』に記されている神道の神々の数で、実際の数ではなく「たくさんの神々」という意味。 神道では信仰の対象によって、それぞれ神がいるため神の総数が曖昧になっている。 そのため八百万の神々と呼ばれた。 |
| 厄(やく) | 災難。わざわい。 |
| 厄年(やくどし) | 災難に遭うことが多いので気をつけるべきだといわれる年。 男は数え年の二五・四二・六一歳,女は一九・三三・三七歳などとされる。 陰陽道で説かれたもの。災厄の多い年。年忌み。 |
| 厄払い(やくばらい) | 厄を払い吉に転ずるための神社でおこなわれるお祓いのこと。厄落としともいう。 厄払いの方法としては神社に参拝して祈願することやお祓いを受けることが一般的。 |
| 厄日(やくび) | 災難に遭った日。 |
| 八尺瓊の勾玉(やさかにのまがたま) | 三種の神器の1つ。 アマテラス が天岩戸に隠れた時に玉祖命が作ってくれた神具。 |
| 八十神(やそがみ) | オオクニヌシ(オオナムチ)の兄たちのこと。 |
| 八咫烏(やたがらす) | 日本神話に登場する神聖な三本足のカラスで、導きの神として有名。 初代天皇である神武天皇を案内したとされ、太陽の化身ともされている。 八咫烏は、天・地・人を象徴する三本の足を持ち、神話や伝説において重要な役割を果たしている。 |
| 八尋殿(やひろどの) | イザナギとイザナミが住んだ 淤能碁呂島(おのごろじま)の家。 |
| 大和(やまと) | 現在の奈良近辺。日本を指す場合もある。 |
| 由緒(ゆいしょ) | 神社が創建された発端やその歴史。 |
| 揖(ゆう) | 30°及び45°のお辞儀のこと。 30°のものを「小揖(しょうゆう)」、 45°のものを「深揖(しんゆう)」と呼ぶ。 ちなみに神職は 15°、30°、45°、60°、90°の お辞儀を使い分けている。 |
| 悠基(ゆき) | 大嘗祭に定められている2つの祭祀のそれぞれの一方の系列に関する名称。 もう一方は「主基」(すき)。 |
| 黄泉の国(よみのくに) | 冥界のこと。日本神話に登場する死後の世界のこと。 |
| 黄泉醜女(よもつしこめ) | 日本の古事記に登場する黄泉の国に住む醜い女性達の総称。 |
| 黄泉比良坂(よもつひらさか) | 日本の神話において黄泉の国と現世の境にあるとされる場所。 |
| 依代(よりしろ) | 神霊が降臨する際に神霊の宿り場となるもの。 |
ら行/神道・神社の用語解説
| 語句 | 意味・解説 |
|---|---|
| 雷神(らいじん) | 日本の民間信仰や神道における雷の神様。 風神と対になって描かれる事が多い。 稲妻を神格化したようなもので太鼓をたたいて雷を起こすとされている。 |
| 霊験(れいげん) | 神仏が人間の祈願に応じて示す、不思議な力や現象のことを指す。 超自然的な力によって、祈願者に利益をもたらすとされている。 神霊の不可思議な感応、効験をいう。 キリスト教における「奇跡」に似た概念として広く知られている。 |
| 霊魂(れいこん) | 一般的にいわれている魂のこと。 神道では古来より肉体と精神は別物と考えられている。健康なときは霊魂と身体が合致している状態で、肉体的な不調(病気や死)は霊魂が身体から離れた状態だということになる。 霊魂は不滅で肉体を離れると、霊魂は祖霊の元へ帰るとされています。 霊魂にはその働きや活動によって様々な呼称があり、直霊、和魂、荒魂、奇魂、幸魂などと呼ばれます。 |
| 例祭(れいさい) | 祭神の由緒や神社の縁故によって選ばれた恒例の大祭。その神社にとって最も重要な祭祀。神社で毎年行われる、もっとも重要な祭祀のこと。 神社が鎮座した日や祭神の忌日(きじつ)など、 特別な由緒のある日に開かれることが多い。 「例大祭(れいたいさい)」と呼ぶこともあり、数年に一度開催している神社もある。 |
| 伶人(れいじん) | 雅楽の職業的楽人の呼称。 |
わ行/神道・神社の用語解説
| 語句 | 意味・解説 |
|---|---|
| 倭(わ) | 中国につけてもらった日本の名前。 |
| 若宮(わかみや) | 本宮の祭神の子を祭った神社のこと。 「若宮」という言葉には、幼少の皇子や皇族の子という意味もある。 |
| 和邇(わに) | 古代日本では口の大きな動物はワニと呼ばれていた。 その時点でワニは日本にいない可能性が高いとされるため古事記でワニの記述もあるが、現在の研究ではサメのことだろうとされている。 |

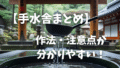
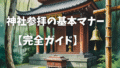
コメント