皆さんは神社に行ったときに「基本的なマナーは絶対に大丈夫」と言えるでしょうか?
今回はそんな不安を一気に解消できる記事となっています。
参拝の本来の目的/願い事の基本
この記事では、神社参拝の基本マナーを【初心者でも迷わないように】分かりやすく解説します。
皆さんは参拝をする時に、お願い事をしているのではないでしょうか?
私も最初は、気持ち程度のお賽銭を入れて神様に自分の願いを祈ることだけしかしていませんでした。(どうしても神様に少しでもご助力いただきたい時は、お賽銭を奮発。なんてこともしていた時期もありました笑)
もちろん、参拝する目的の1つに願い事をするというのは間違いではありませんし、
なんなら、これが最大の目的と思えるくらいです。祈願というのはそういうものであり、だからこそ、その部分だけが有名になっていったのかもしれません。
しかし、本来の参拝の目的は神様にお願いをすることではなく、神様に日頃の感謝を伝えるためのものです。
古代日本では神社に参拝して町や国の豊作や大漁などの感謝を込めて祈ってきました。
そのため参拝するときには、まず日頃の感謝をして、そのあとに「これからもお守りくださるよう」気持ちを込めます。
『神様に感謝の気持ちを持った上でお願い事をする』ということが大切になってきます。
・どんな願い事でもいいの?神社参拝の祈願内容について
・「将来お金持ちになりたい」
・「受験絶対に合格させて」
・「公務員とか社長とか良い仕事に就きたい」
(↑すいません、幼少の頃に私がした安直な願いの数々です。笑)
参拝したきに神様に願い事をするのは、悪いことではありません。
しかし、本来の目的とは少しズレています。
順を追って説明すると、日頃を見守ってくれている神様に平穏無事を感謝するために参拝するというのが本来の目的になります。私のように、努力もせずに全て神頼みにしても叶いません。
目標の達成や成功には自分自身の努力が必須です。
願い事は自分自身の努力や頑張りを前提として神様に伝えましょう
ならどのように願い事をするのがいいのか?
すべてを神様にお願いするのではなく、自分自身ではどうにもならないことをお願いします。
「努力を惜しまず勉強するので合格するためにご助力ください」
「一生懸命に仕事に励むので家族みんなが健康で過ごせますように」
「周りに迷惑や心配をかけないように、自分で出来る事は全て頑張るので病気の原因が一日でも早く分かりますように」
といったように努力する内容や周りの幸せも考えた上で願い事をするのが好ま
【図解付き】神社参拝の基本作法と流れ|二礼二拍手一礼まで解説
参拝方法
「再拝(二礼)して二拍手して、その後に神様に願い事を伝えて、最後にまた一拝(一礼)する」
これが神社での拝礼の基本的な流れです。
1.神前に進み、賽銭箱にお賽銭を入れます。
このとき乱暴になるべく丁寧に投げ入れてください。
2.賽銭を投げ入れたら鈴を鳴らします。
お賽銭箱の真上には鈴がつるされています。
この音色は参拝者を払い清めるという意味があります。
またお賽銭には自身の穢れを移し祓うといった意味もあります。
※お賽銭投入、鈴を鳴らす、の順番はどちらでも問題ありません。
3.次に二拝二拍手一拝です。
①二拝
拝(礼)は姿勢を正して腰を90度に折りお辞儀をします。この時の拝(礼)は2度行います。
②二拍手
次に胸の高さで両手を合わせ、右手を少し下にずらします。
(↑神様を讃える気持ちを表現するための所作)
その後2回手を打ちます。
☆【このタイミングで願い事をします】
③一拝
最後にもう1度拝(礼)をします。

拝礼の作法
二拝二拍手一拝のうちの拍手は、柏の葉のように打ち合わせるため、
一般には「柏手(かしわで)を打つ」ともいわれています。
神前で打つ柏手も、神様にご加護をいただいていることを感謝して打つものです。
願い事の方法/どうやって伝えるのがいい?
自己紹介をする
住所や名前を伝えるのは、自分が「どこの誰なのか」を正しく伝えるためです。
多く参拝者が祈願しているので、名前と住所を伝えて神様に認識してもらいましょう。
神様にも名前と祀られている住所があることで私たちも認識できているからです。
感謝を伝える
本来の参拝は日頃の感謝をするためです。
例)「いつもお守りくださってありがとうございます」
「何事もなく平穏に生活させていただきありがとうございます」
といった気持ちを伝えましょう。
願い事をする
願い事は上記の注意点を踏まえて祈願しましょう。
病気平癒、合格祈願、商売繁盛、開運招福など自身に合ったものを祈願することは、とても良いですが、沢山の種類の願い事や一度にあれもこれもと欲張ってしまうのはいただけません。
神様も混乱してしまうので願い事は一つにしておきましょう。
参拝のとき願い事は声に出した方がいいの?
これは言霊信仰の考え方です。
日本では古くから言葉には霊力があると信じられており、自分が発した言葉が実現すると考えられてきました。
このため願い事も声に出すほうが叶いやすいと信じられています。
また願い事を声に出すのは言霊信仰だけではなく「潜在意識に浸透させることで叶えやすくする」という心理学でいう所の宣言効果のような考え方もできます。
おすすめは声を出す事ですが、大きな声で叫んでも周りに迷惑をかけてしまいます。
声の大きさは自分自身が聞こえる程度で問題ありません。
「言葉にする」ということが大事だからです。
【驚愕】二拝二拍手一拝が全てではない!?
神社は基本的にはどこも二拝二拍手一拝が一般的となっています。
しかし、いくつかの神社では特殊な拝礼方法を行っているところがあります。
その際は神社の作法に従ってお参りしましょう。
例えば、『二拝四拍手一拝』といって4回、柏手を打つ神社もあります。
有名なところだと、出雲大社や宇佐神宮、彌彦神社などがそれにあたります。
そういったところは、お賽銭箱の横など目に付くところにお参り方法や看板が掲げられているため確認しておくのが良いです。
すいの体験と参拝まとめ
私がこの参拝マナーを知った時は幼いながらに衝撃的でした。
思ったのが「確かに願えばなんでも叶えてくれるならドラゴンボールの神龍とほぼ一緒だ。そんな都合のいい世界じゃなかった。」と。笑
個人的な考え方ですが、神前ではもとより、日頃から誰に対しても感謝の気持ちをもって生活して行くことが大切であって、その気持ちは自分の言葉や行動・考え方にまで影響してくる。
それが周りにも影響を与え神様にも認めてもらい、巡り巡って自分の幸せにつながってくるよってことが参拝の本質なのかなって思ったりします。
皆さんはどんな風に考えをお持ちでしょうか?
良かったらコメントなどで私にも教えてくれると嬉しいです。
参拝で使う言葉や神社に関する用語は、神道・神社の用語解説で詳しくまとめてあります。
ほとんどの神社にある手水舎についての作法もこちらで解説しています。
もっと詳しく知りたい方は【神道用語集】もぜひチェックしてみてください!

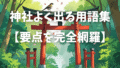

コメント